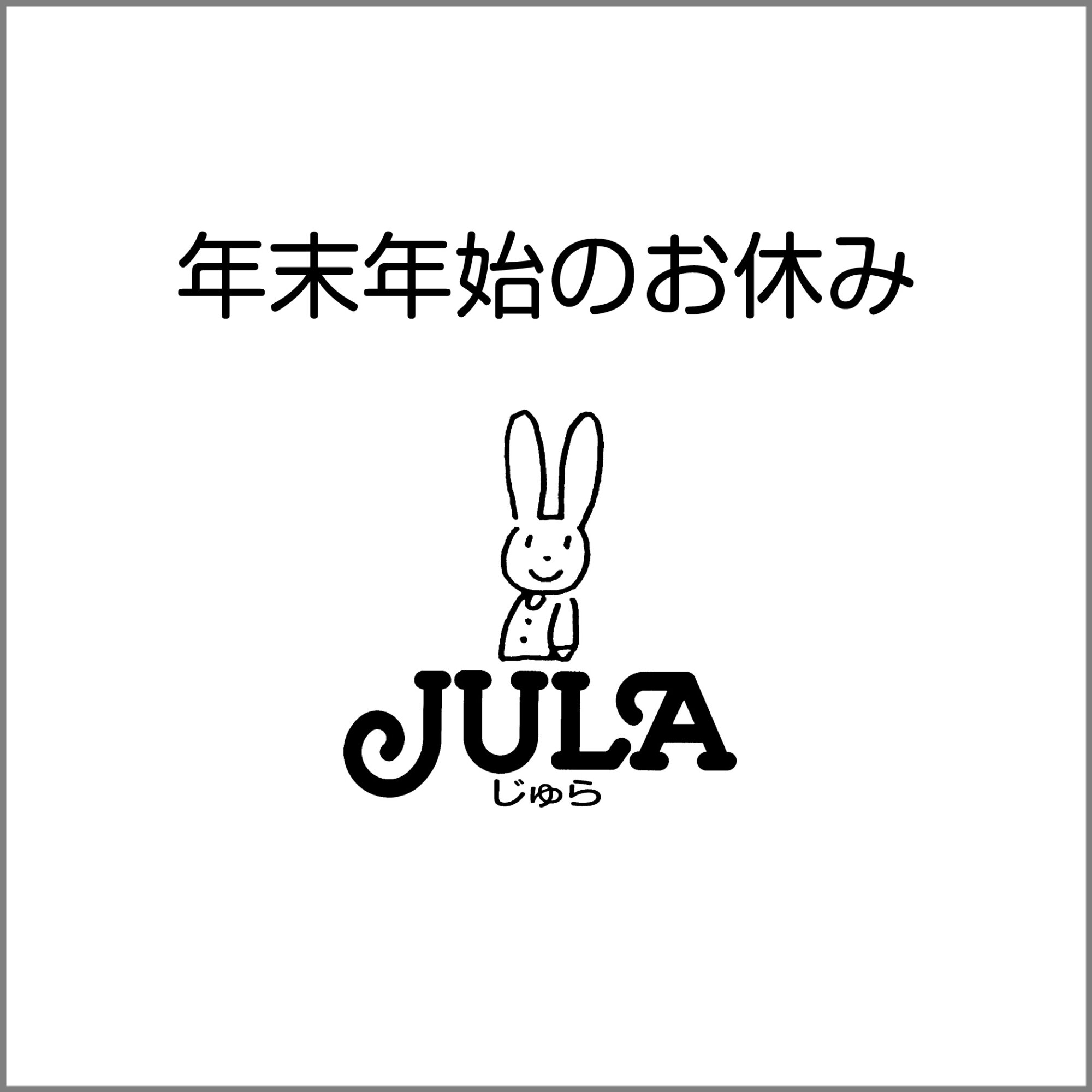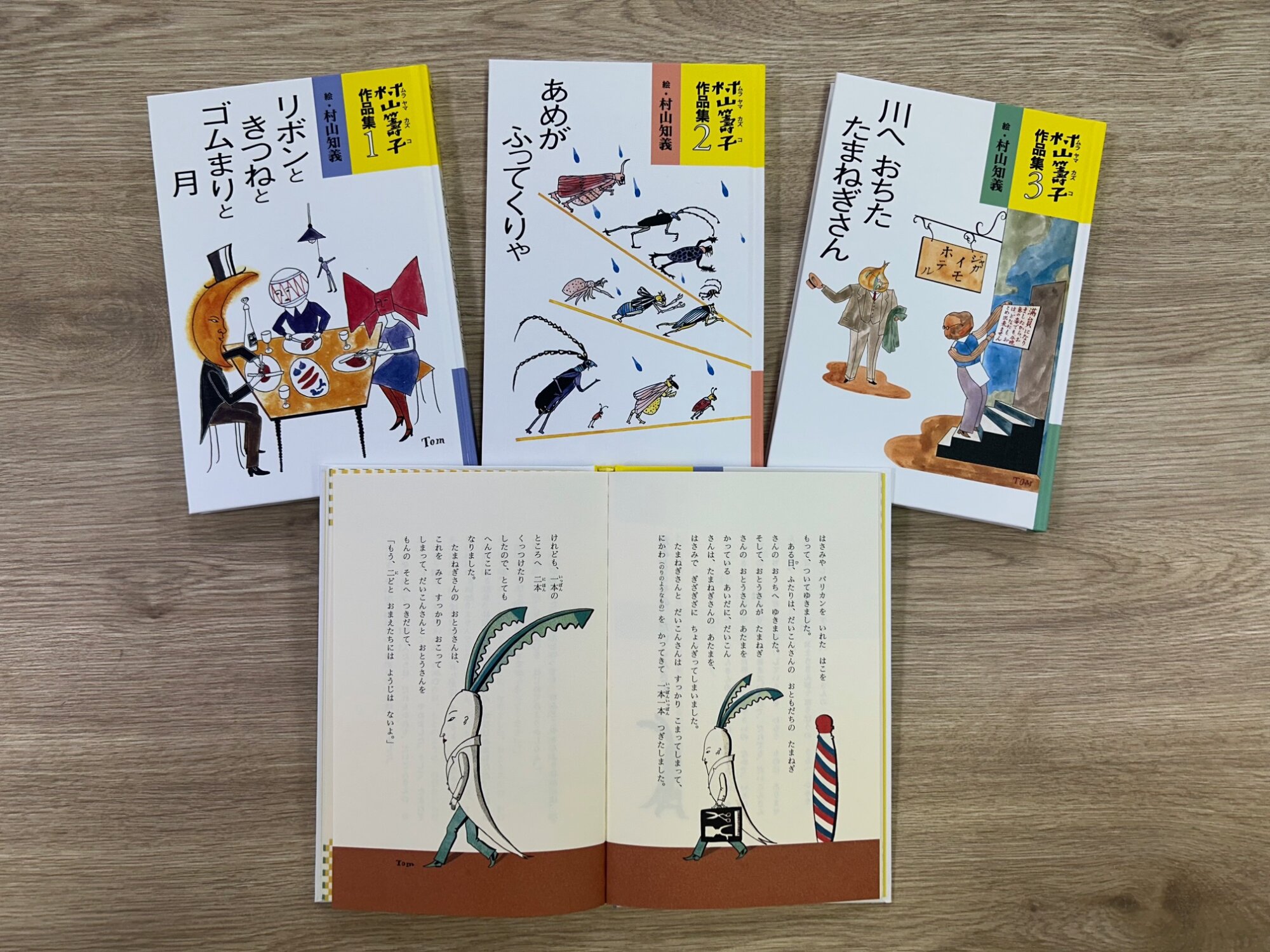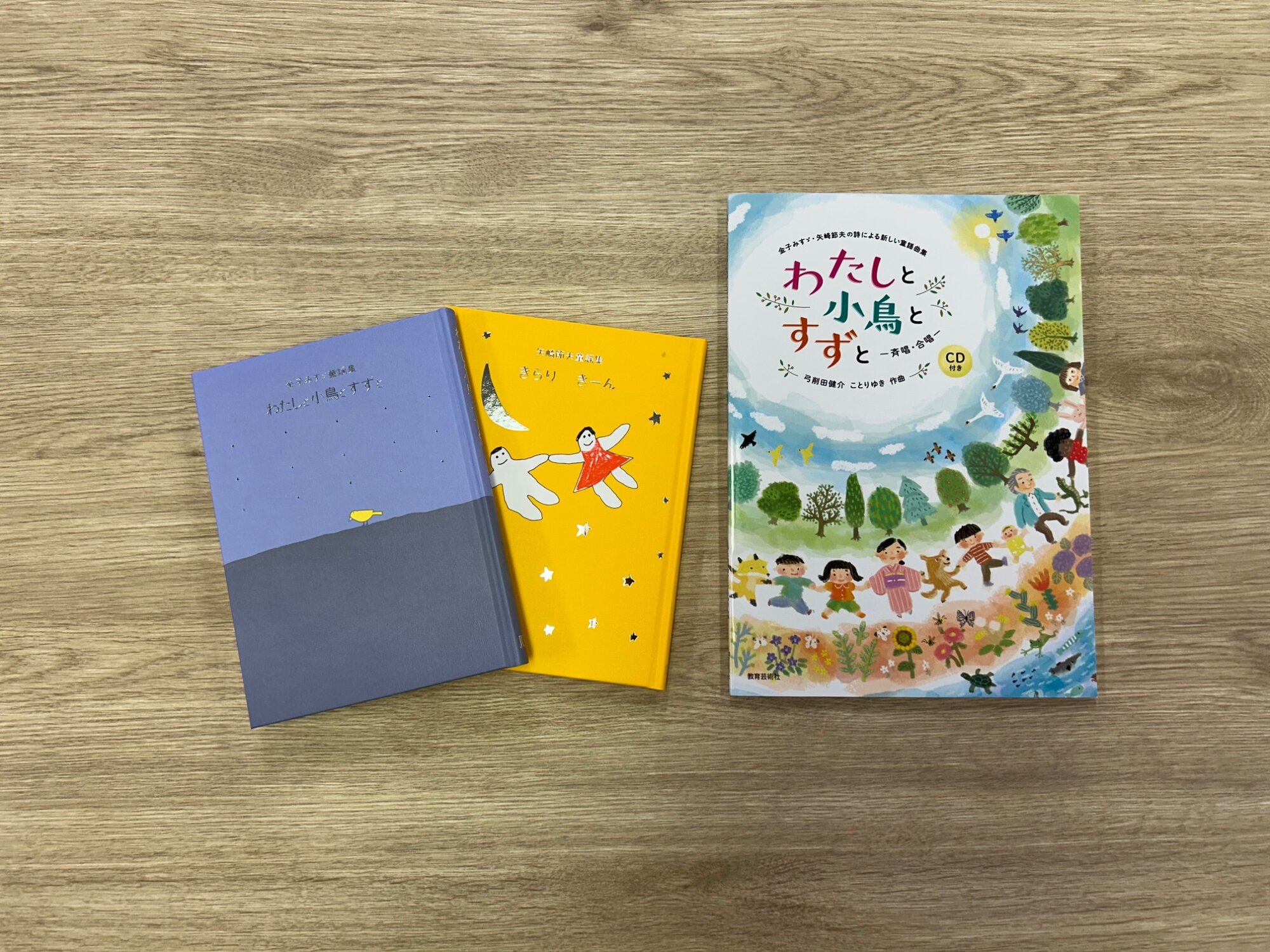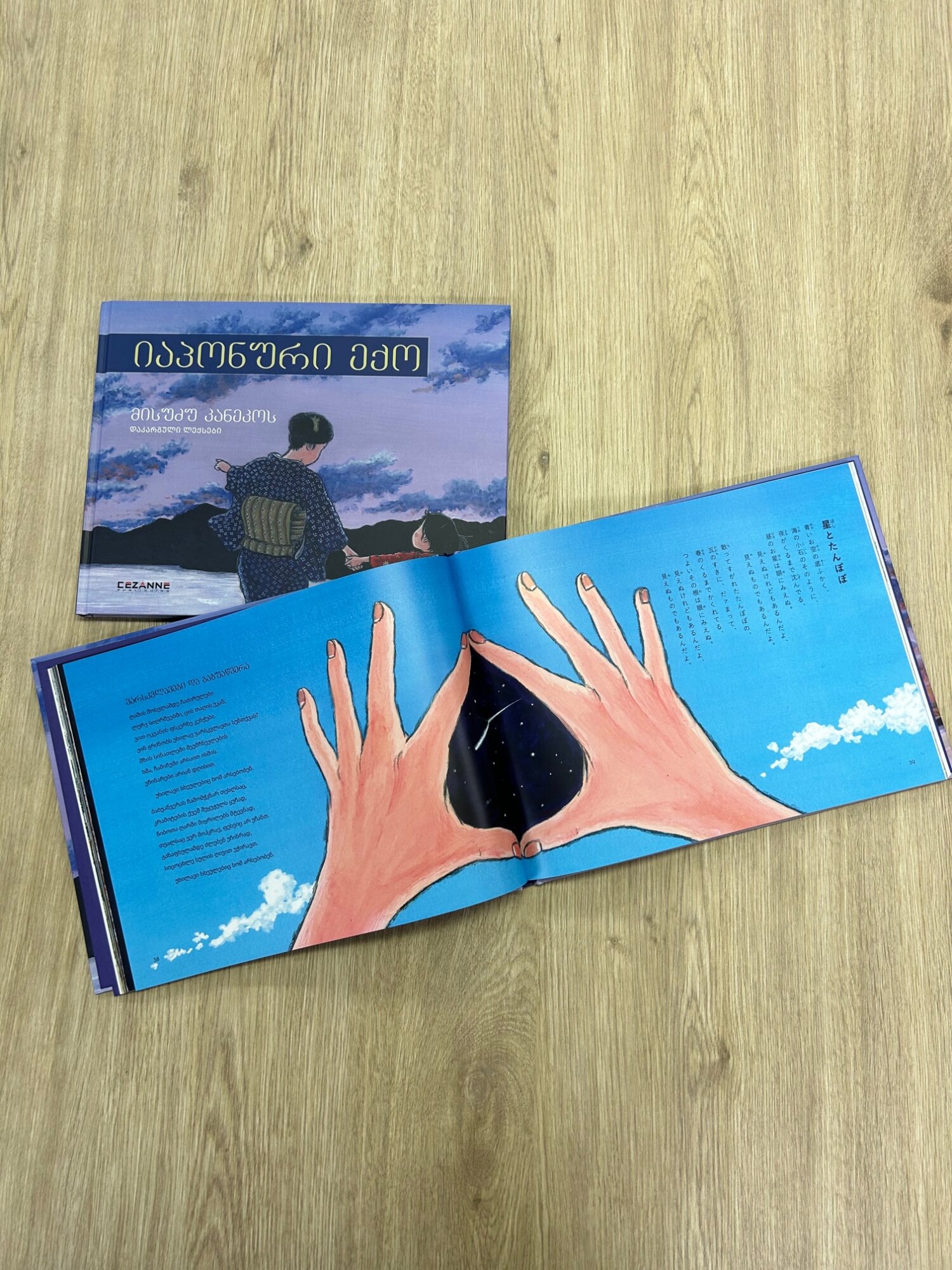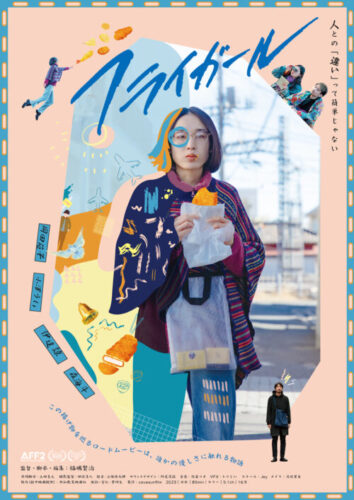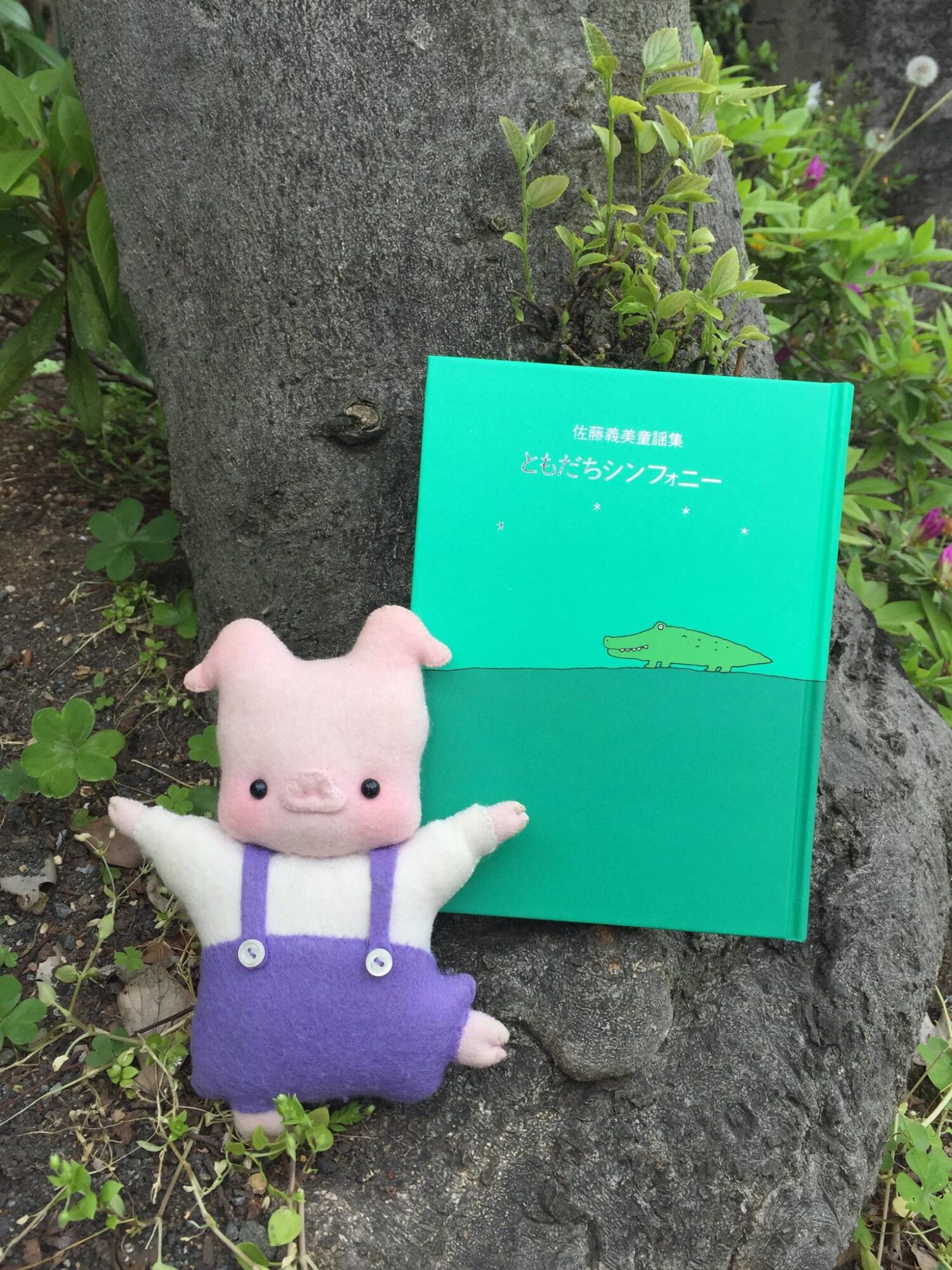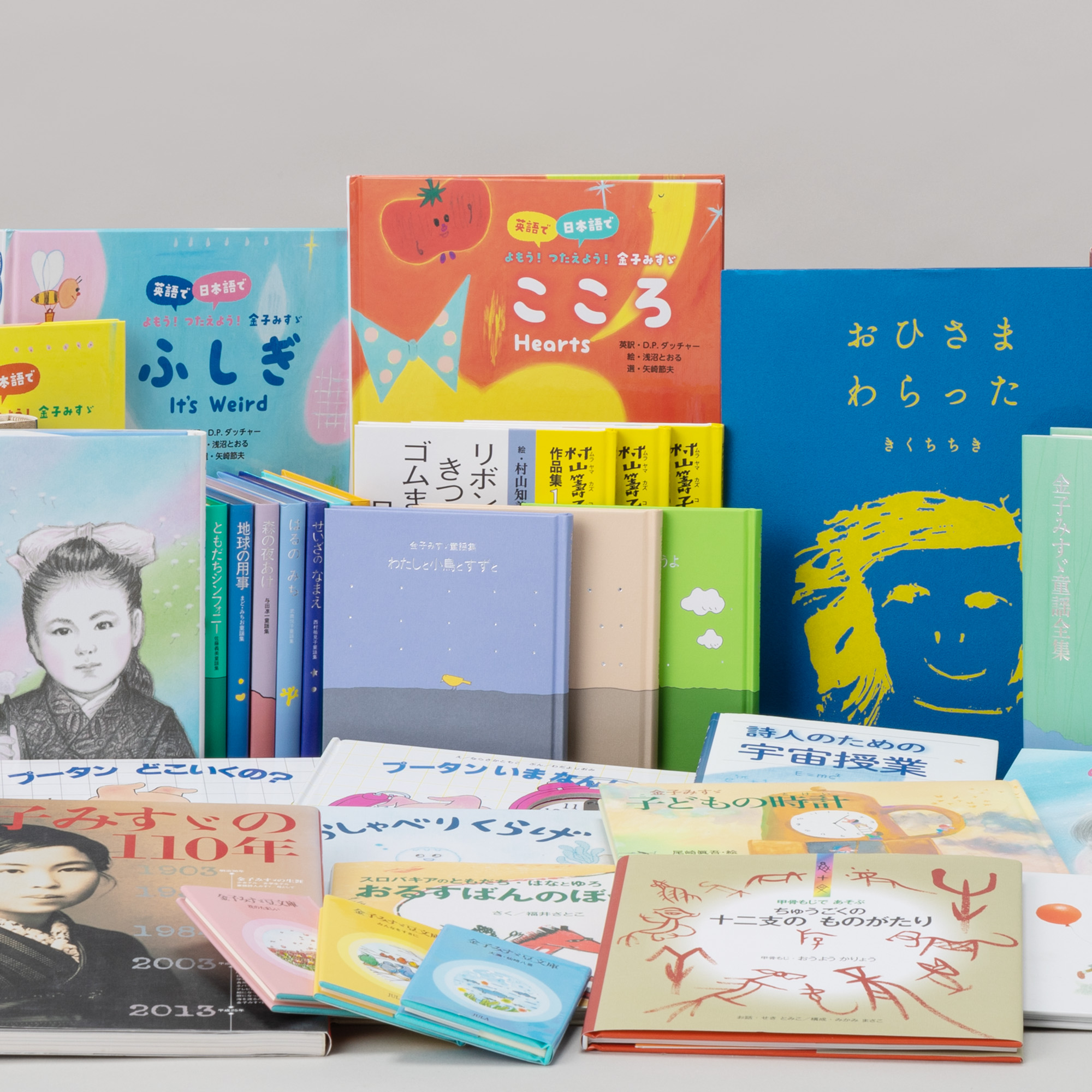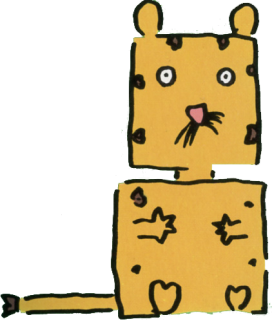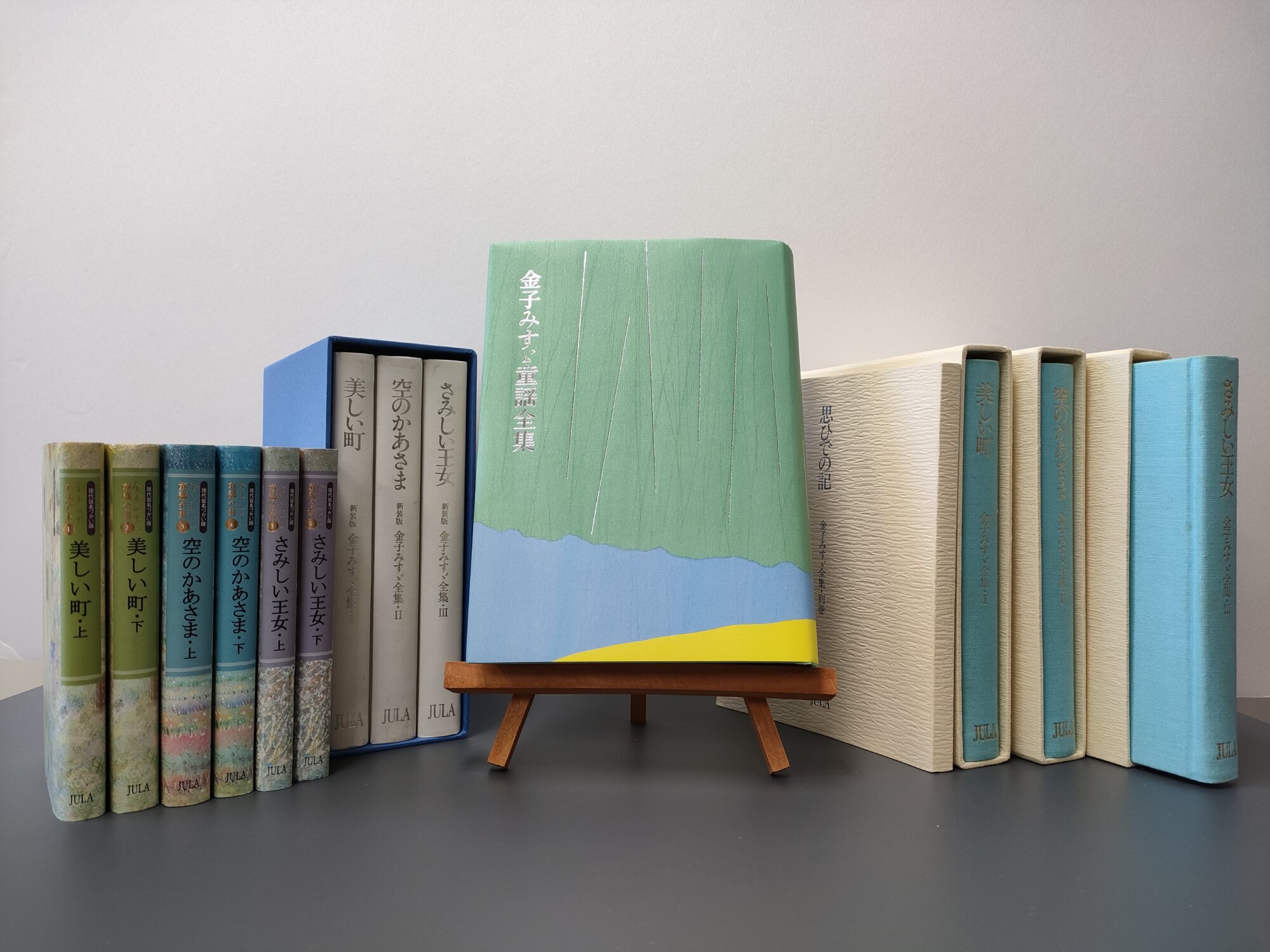




金子みすゞ 今月の詩
毎月、詩を一編ご紹介いたします
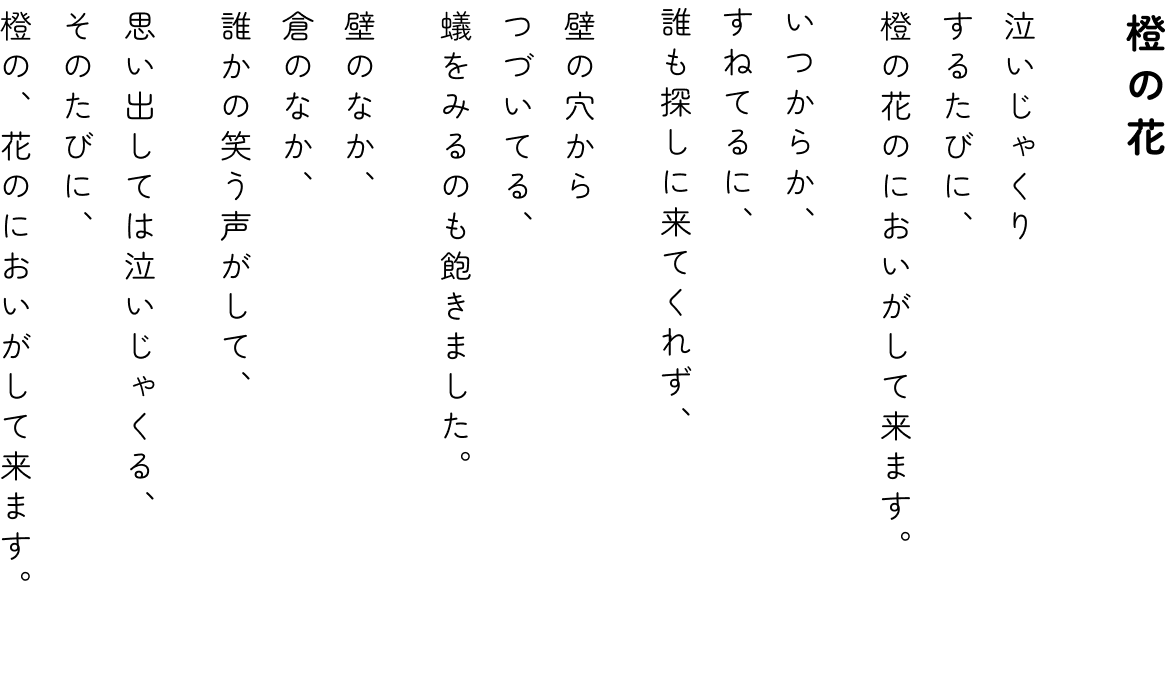
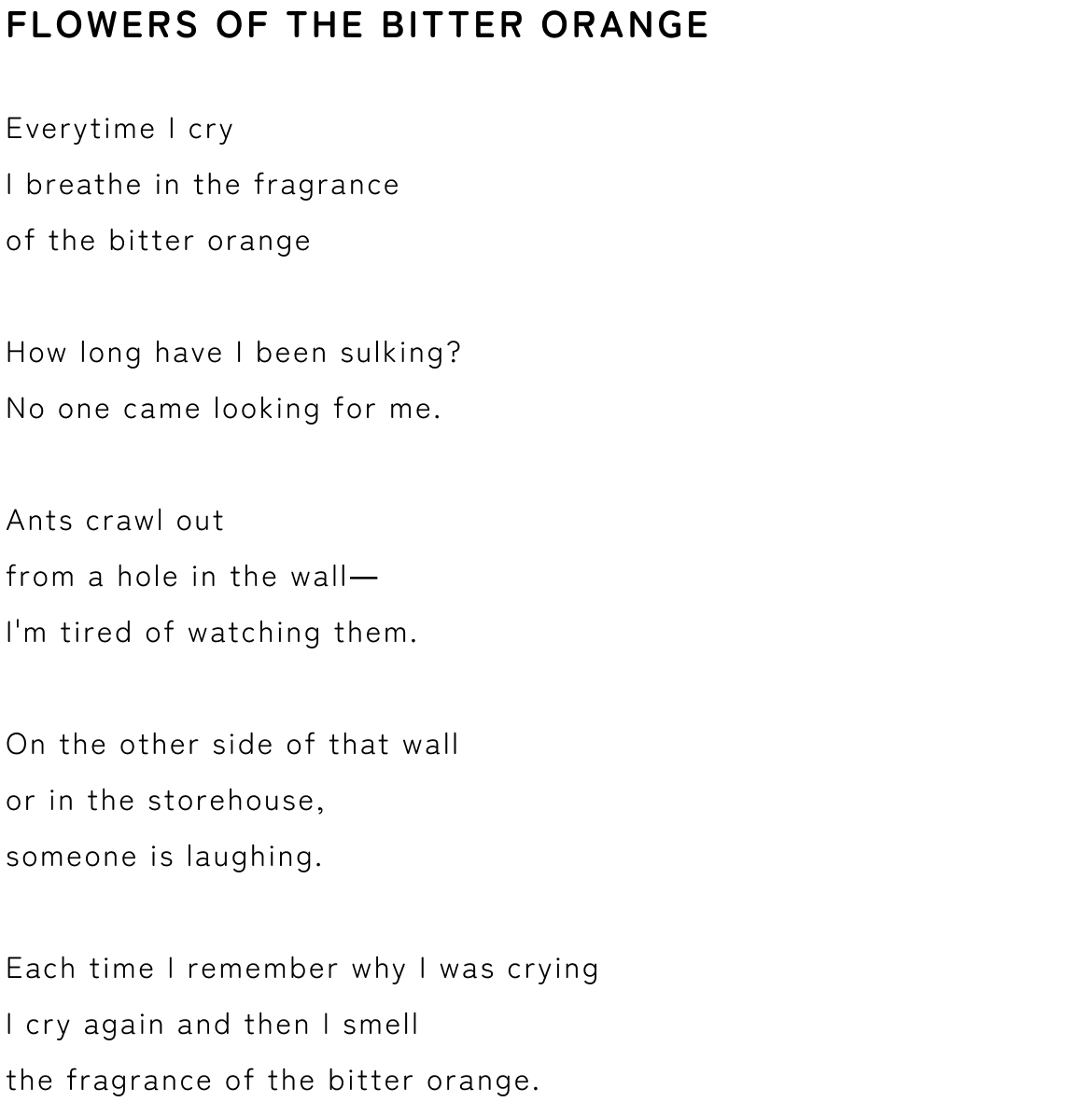
『金子みすゞ童謡全集』(JULA出版局)より
Translations by Sally Ito & Michiko Tsuboi / JULA
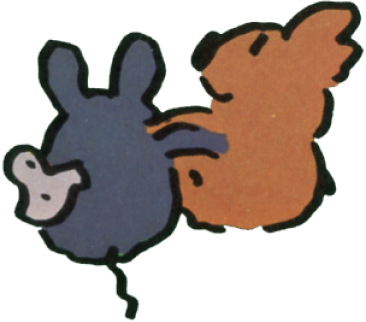
展示 イベント メディア協力
-
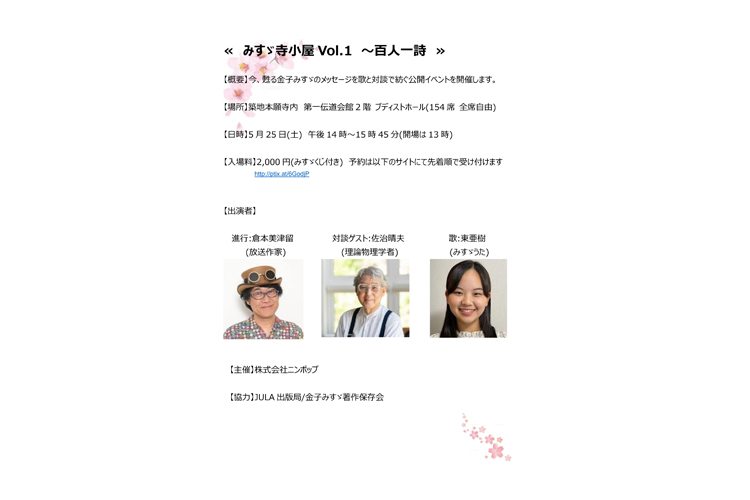
2024年5月25日(土)14時開演
築地本願寺ブディストホール
みすゞ寺子屋Vol.1 ~百人一詩
-
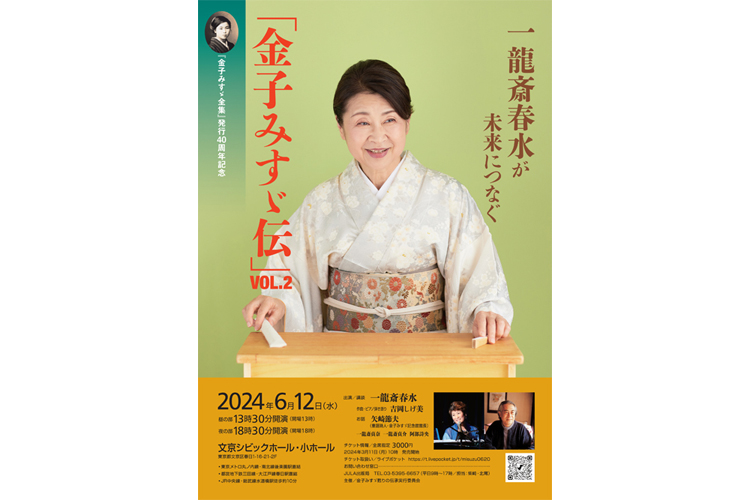
2024年6月12日(水) 昼の部 13時30分開演 / 夜の部 18時30分開演
文京シビックホール・小ホール
一龍斎春水が未来につなぐ「金子みすゞ伝」VOL.2
-
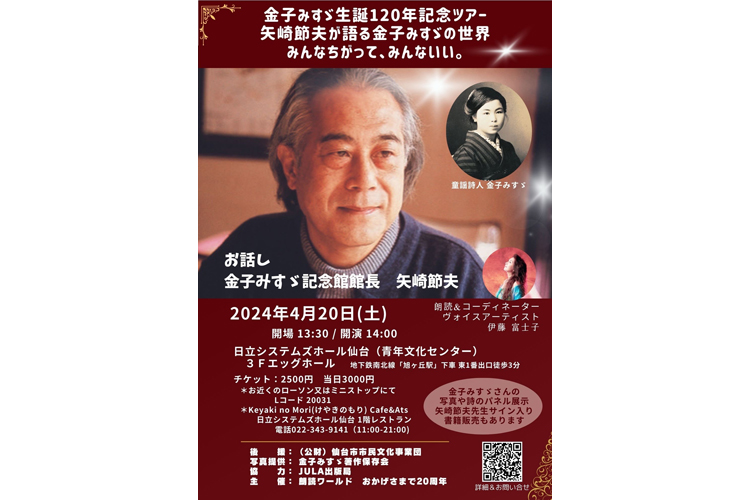
2024年4月20日(土)14時開演
日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター)3Fエッグホール
金子みすゞ生誕120年記念ツアー 矢崎節夫が語る金子みすゞの世界 みんなちがって、みんないい。
-
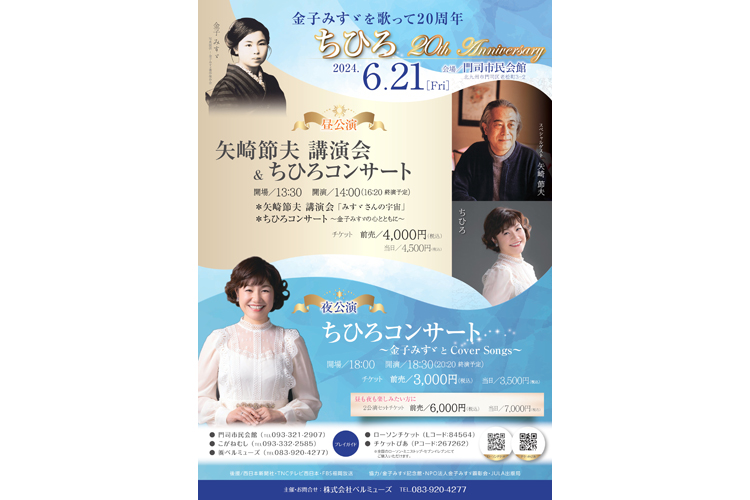
2024年6月21日(金) 昼公演 14時開演 / 夜公演 18時30分開演
門司市民会館
ちひろ 20th Anniversary ~金子みすゞを歌って20周年~
-

(終了)エフエム山口・TOKYO FM共同制作 金子みすゞ詩作100年記念特別番組「見えぬけれども あるんだよ」
-
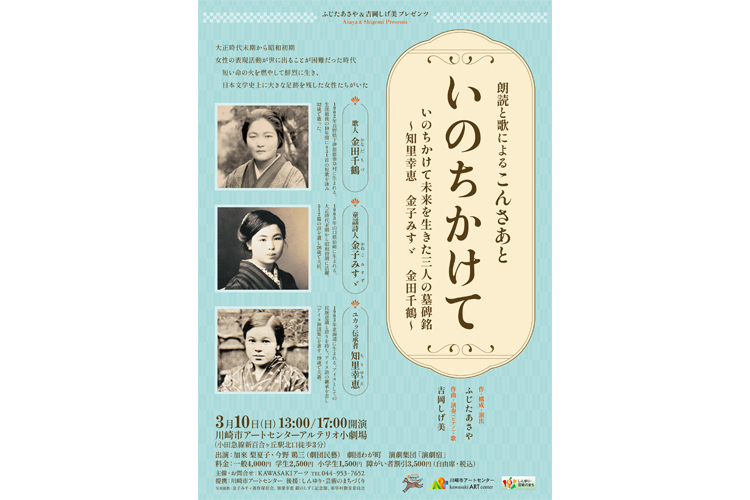
2024年3月10日(日)第一公演 13時開演/第二公演 17時開演
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
(終了)朗読と歌によるこんさあと「いのちかけて」~知里幸恵、金子みすゞ、金田千鶴~
-

2024年2月3日(土)14時開演
山口県立劇場ルネッサながと・劇場(文化ホール)
(終了)萩山口信用金庫PRESENTS「金子みすゞ生誕120年 ちひろコンサート 明るいほうへ」
-
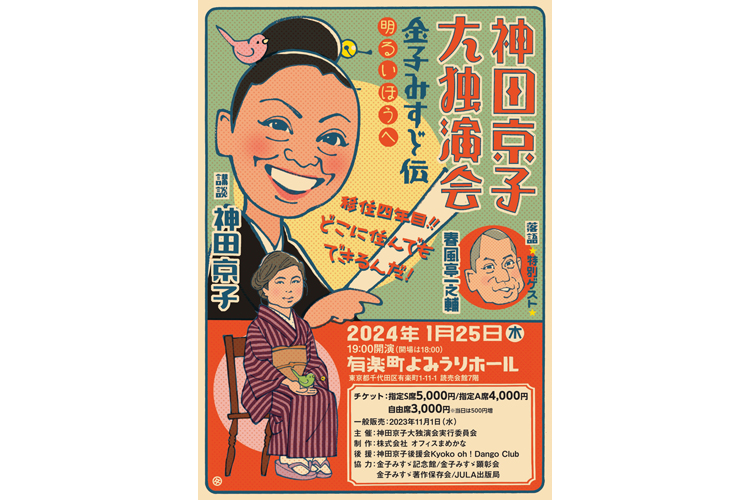
2024年1月25日(木)19時開演
有楽町よみうりホール
(終了)神田京子大独演会 ~金子みすゞ伝 明るいほうへ~
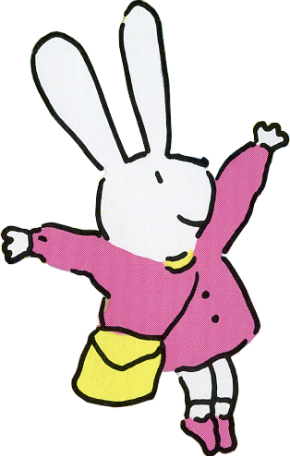
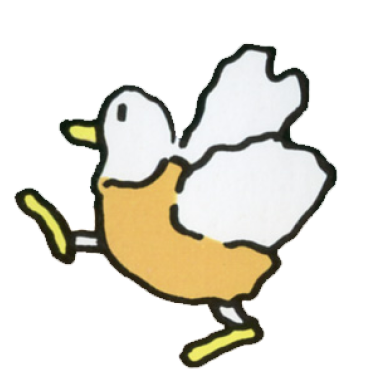

写真提供:金子みすゞ著作保存会
金子みすゞ
だれにでもわかるやさしい言葉で、
今の私たちのこころにもひびく童謡を書いた金子みすゞ。
山口県に生まれ、20歳から作品を発表。
「若き童謡詩人の巨星」と期待されましたが、
26歳の若さで亡くなりました。
いちどは忘れられかけたみすゞですが、
今ではふるさとに記念館ができ、
14の言語に翻訳されるなど、
その魅力はどんどん広がっています。